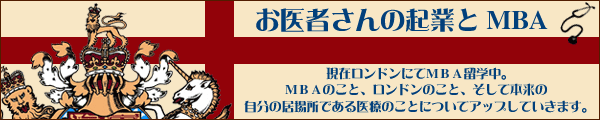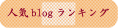血圧管理
来週のテストの嵐の現実逃避の意味も込めて医療ネタを。
日本で医者として働いていたとき、よく高血圧の患者さんを診ることがあった。
そこで思ったことが今日のトピック。
健康診断やスポーツジムにある血圧計、また自分で持っている血圧計など、さまざまな方法で
自分の血圧を血圧が高いということを知り病院に初診で来る。
当然治療が必要な人が多いのだが、中には治療をまったく必要としていないことも多い。
例としては…医療関係者がいると緊張しちゃう人や、スポーツをしたあとに計測する人、あわただしい時間帯にばたばたしながら計測しちゃう人、など。
ここから先は実際に血圧が高いと以前言われた人、また現在血圧治療中の方に是非やっていただきたいことです。
ポイントは「定期的に」「安静にしているとき」「記録をつけて」です。
自分の患者さんにアドバイスする際には二つの道具を手に入れてもらうことにしています。
1.血圧計
2.ノート
血圧計は自動血圧計で(誰も手動だと思ってもいないでしょうけど)。手首タイプと上腕タイプのどちらがいいのかをよく聞かれますが、僕の好みは上腕タイプ。完全に好みの問題ですが。手首タイプは結果が高めに出ます。
ノートはどんなノートでも可。3列の表を作るので罫線が入っているものがいいです。
時間:できれば朝夜1回ずつ。
朝は起きて排尿後、朝食前がベスト。起床後1時間以内に。
夜は寝る前。
なんとなく同じ時間帯というニュアンスで十分です。
安静時というのが大前提。
記録:書くものは<日付・おおまかな時間(例:22時)><血圧(例:120/80)><心拍数>の3点。
これを3列の表に、測るごとに記録。
初診の際にはこれを1週間ほど記録して、診てもらう先生に確認してもらうといいです。
すでに血圧治療中の方はそれを常につけ続け、受診のたびに提出してください。
そうすることで実際に自分が血圧が高いのか低いのか、治療中の人は降圧剤の分量があっているか否かをしっかりとチェックすることが出来ます。
(注意:血圧の薬を自分の判断で飲んだり飲まなかったり、また薬の量を自己判断で減らしたりすることだけは絶対にしてはいけません。薬の調節はかかっている医師にご相談を)
家庭での血圧高い低いという基準は135/85
実際に薬での治療を考えるのは一般的に160/95あたりから、という先生が多いようです。
また機会があったら予防も含めてアップします。
応援のカプセルクリックお願いします。